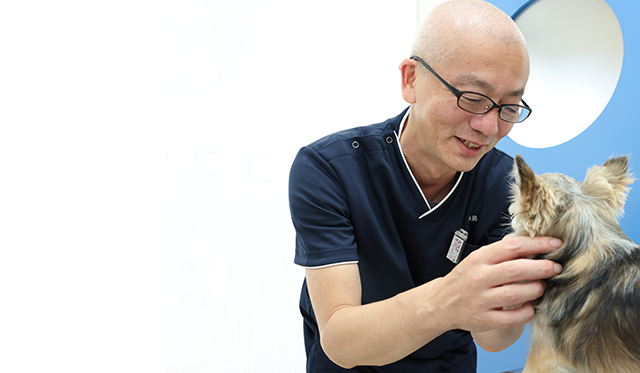当院の内分泌科
内分泌科で代表的な病気の一部をご紹介します。
犬の糖尿病
糖尿病とはインスリンの不足や欠乏により高血糖が生じ、様々な代謝異常を生じる病気です。犬の糖尿病の原因には、膵島(膵臓の中のインスリンを分泌する部分)萎縮、クッシング症候群、黄体期糖尿病(不妊手術をしていない雌犬)、膵炎、医原性(ステロイド剤の長期投与)などがあります。
症状
初期には多飲多尿(飲水量と尿量が多い)、多食、体重減少などが見られますが、進行すると元気消失、嘔吐、下痢などもみられるようになります。
診断
多飲多尿、体重減少などの特徴的な臨床症状に加えて、持続的な空腹時高血糖(180mg/dl以上)、持続的な尿糖があれば糖尿病と診断します。
治療
治療の目標は多飲多尿や体重減少を改善し、白内障や腎症などの合併症を予防することによって犬とご家族の生活の質を改善することにあります。副腎疾患や卵巣疾患が解決できれば糖尿病が治ることもありますが、基礎疾患の治療をしても糖尿病が治らない場合にはインスリン注射による血糖コントロールが必要となります。雌犬の発情後に卵巣から分泌されるプロゲステロンというホルモンは強力なインスリン抵抗性を持っていて、糖尿病の治療中に発情があると血糖のコントロールが著しく困難になります。よって糖尿病と診断された不妊手術をしていない雌犬においては可能な限り卵巣子宮摘出術を行います。高繊維食などの食事療法が同時に行われます。
猫の糖尿病
猫の糖尿病の原因疾患には、2型糖尿病(ヒトと同じ糖尿病)、膵炎、先端巨大症などがありますが、2型糖尿病と膵炎が2大原因疾患となっています。
| 2型糖尿病 | 膵炎による糖尿病 | |
|---|---|---|
| 性差 | 去勢オスがほとんど | 雌雄に差はない |
| 体型 | 肥満(あるいいは過去に肥満) 体格が大きい |
現在過去に肥満経歴なし むしろ痩せている |
| 食欲 | 多食 | ムラあり |
| 消化器症状 | なし | 時々嘔吐・軟便 |
| インスリン | 安定して効く | 普段は効きすぎる 不調時は効かない |
2型糖尿病に膵炎が併発しているというようなきれいに分けられない病態もありますが、どちらの原因によって糖尿病になったかを考えておくことが重要です。
症状
症状は犬と同様で、初期には多飲多尿(飲水量と尿量が多い)、多食、体重減少などが見られますが、進行すると元気消失、嘔吐、下痢などもみられるようになります。猫では慢性の糖尿病による長期の高血糖が続くと、後肢の麻痺を特徴とした神経症状が見られることがあります。
診断
多飲多尿、体重減少などの特徴的な臨床症状に加えて、持続的な空腹時高血糖(300mg/dl以上)、持続的な尿糖があれば糖尿病と診断します。
治療
猫の糖尿病の治療における大原則は、安定した食欲です。
食べてくれなければインスリン治療ができません。よって食欲不振がある場合、糖尿病以外の食欲が不安定になるすべての疾患の治療をします。
毎日の食事を毎日一定量食べてくれるようにします。
食事の内容は一般的には猫が毎日安定して食べてくれるもの(シニア用の一般食など)が奨められます。
2型糖尿病の猫(大きい太った猫)については糖尿病治療食、膵炎によって糖尿病になっている猫については消化器疾患用の治療食などが奨められます。
猫の糖尿病は初診時に重度の糖尿病になっていることが多く、ヒトで行われているような血糖降下薬による治療は第1選択とはなりません。よってインスリン注射による治療が行われます。通常、インスリン注射は1日2回行われます。目標血糖値は100~300mg/dLです。
インスリンは筋肉・脂肪・肝臓で作用しますが、痩せている猫では筋肉や脂肪が少ないのでインスリンが効きにくくなっています。しかし、肥満もインスリンが効きにくくなります。よって理想的な体重の維持も重要です。
治療のゴールは、理想的な体重を維持し、インスリン注射によって血糖値を100~300mg/dLにして、この状態を長期間維持することです。
犬の副腎皮質機能亢進症
副腎皮質機能亢進症とは、副腎からの過剰なコルチゾール分泌が慢性的に起こることで特徴的な臨床症状を呈する症候群で、クッシング症候群とも呼ばれます。
コルチゾールは生体を維持するために不可欠なホルモンですが、ホルモン過剰が慢性的に起こると代謝異常、易感染性などの負の側面が現れるようになります。
副腎皮質機能亢進症は、その発症原因により下垂体性と副腎腫瘍性に分類されます。犬では、下垂体性が約90%、副腎腫瘍性が約10%と報告されています。
症状
多飲多尿、多食、パンティング(ハアハアする)、腹囲膨満(お腹が出る)、脱毛、筋力低下、高血圧などが見られます。
診断
特徴的な臨床上の所見に加えて、ACTH刺激試験や低用量デキサメサゾン抑制試験、血漿ACTH濃度などの血液検査、超音波検査、尿検査などによって診断します。下垂体巨大腺腫が疑われるときにはCT検査MRI検査などの画像検査が行われます。
治療
体内でコルチゾール合成を抑制する治療薬の内服による内科治療や放射線治療、外科治療などが行われます。
犬のアジソン病(副腎皮質機能低下症)
アジソン病とは、副腎皮質の85-90%程度が破壊されることによってグルココルチコイド(コルチゾール)やミネラルコルチコイド(アルドステロン)が不足することで様々な症状を表す病気です。
症状
症状は元気消失、食欲不振、震え、嘔吐、下痢などですが、これらの症状は通常は副腎皮質機能の90%が失われると発現します。初期にはまだ予備能力が残っているために犬にペットホテルやトリミング、通院や入院などのストレスがかかった時だけ間欠的に症状が発現します。これらの症状を見過ごしていると、その頻度は次第のに高くなり、最終的にはショック状態になります。
診断
血液検査で電解質異常やコルチゾール値の低下、腹部超音波検査で副腎の萎縮などを確認します。
治療
ショック状態のような急性期には静脈内輸液が行われますが、維持治療としては酢酸フルドロコルチゾン(フロリネフ)の内服かピバル酸デソキシコルチコステロン(DOCP)の3-4週間隔での注射が行われます。
犬の甲状腺機能低下症
甲状腺機能低下症は、甲状腺の萎縮による血中甲状腺ホルモン濃度の低下によって様々な症状を呈する病気です。
症状
元気消失、脱毛などの被毛の異常、色素沈着や角化異常などの皮膚の異常、再発性の皮膚炎や外耳炎、肥満などが見られます。発生頻度が低い症状としては、ふらつきや顔面神経麻痺、前庭疾患などの神経症状、寒冷不耐症や虚脱、昏睡などがあります。
診断
血液検査によって甲状腺ホルモンと甲状腺刺激ホルモンの測定を行って診断します。
治療
足らない甲状腺ホルモンを補充する補充療法によって治療します。具体的にはレボチロキシンナトリウムの内服が行われます。1-2か月毎に現在の投与量が適正かどうかの血液検査が行われます。
猫の甲状腺機能亢進症
猫の甲状腺機能亢進症は糖尿病と並んで代表的な猫の内分泌疾患です。
甲状腺の過形成、腺腫、腺癌などによって甲状腺ホルモンが過剰になることによって様々な症状が出ます。
症状
体重減少、食欲低下~亢進、多飲多尿、嘔吐や下痢、被毛がバサバサになるなどが見られます。
診断
血液検査で血中の甲状腺ホルモン濃度が高値であれば甲状腺機能亢進症と診断します。
全身状態の把握のための全身のレントゲン検査や超音波検査(甲状腺、腹部、心臓)などが行われます。
治療
抗甲状腺薬であるチアマゾールの内服、ヨウ素制限食、外科手術が行われます。
通常はチアマゾールの内服かヨウ素制限食で治療を開始しこれらによって症状が改善し甲状腺ホルモンの値が低値になれば、そのまま治療を継続します。ただし、内科療法は甲状腺ホルモンの産生と分泌を抑制しているだけで完治ではありません。
内科療法が行われた場合は、症状の確認、体重測定、血中甲状腺ホルモン濃度の測定が定期的に行われます。
甲状腺機能亢進症の治療によって今まで隠れていた慢性腎臓病が顕在化することがよくあります。
慢性腎臓病の定義からお話しますと、慢性腎臓病とはある一定期間腎障害か腎機能低下が持続していた場合に慢性腎臓病とするということになっています。腎機能のマーカーとして血清クレアチニン濃度が用いられていますが、クレアチニンは筋肉から放出されますので甲状腺機能亢進症のような筋肉が少なくなる病気では低値に出やすくなるので、慢性腎臓病があってもまるで腎臓機能が保たれているような数字になることがあります。また甲状腺機能亢進症では循環血液量の増加による腎臓の過還流がおこり、さらに血清クレアチニン濃度が下がります。以上のような要因から慢性腎臓病があっても治療前にはわからないけれど、治療によって筋肉量と循環血液量が本来の状態に戻ったら実は慢性腎臓病だったということが比較的よくあります。
そもそも甲状腺機能亢進症になる猫は比較的高齢であり、慢性腎臓病のリスクは高いと思われます。猫が甲状腺機能亢進症と診断された時点で、慢性腎臓病が隠れている確率は20-40%と報告されています。
外科手術のメリットは、患側の甲状腺を摘出することでそれ以後の投薬や食事療法が不要になることです。内科療法によって血中甲状腺ホルモン濃度が低下していて、猫の心血管系症状が改善し、隠れていた慢性腎臓病が顕在化せず、猫のご家族が外科手術を望めば、外科手術を考慮します。