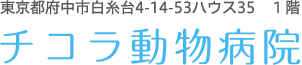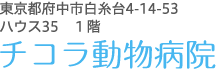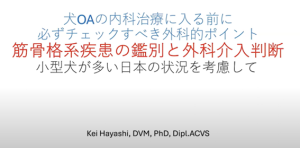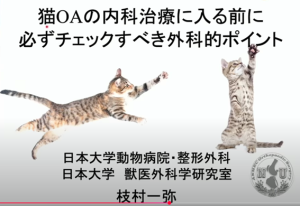-

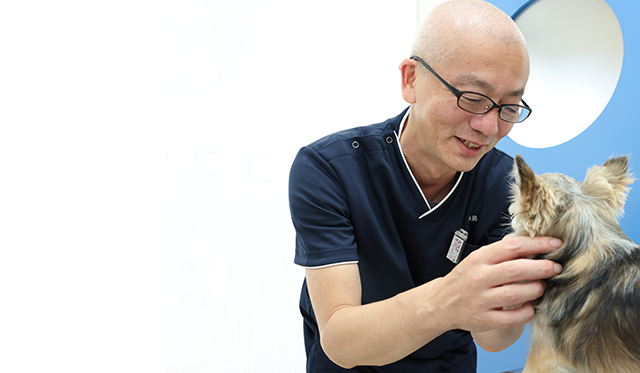
-
抗NGF抗体治療に入る前に知っておくべき外科と内科


抗NGF抗体治療に入る前に知っておくべき外科と内科
2025年10月08日
抗NGF抗体治療に入る前に知っておくべき外科と内科というwebセミナーを視聴しました。
講師はノースカロライナ州立大学の榎本昌孝先生とコーネル大学教授で米国獣医外科専門医でもある林慶先生、日本大学獣医外科学研究室教授の枝村一弥先生の3人でした。
まずは抗NGF抗体とは何かからご説明します。
NGF=Nerve Growth Factorとは神経成長因子といって成長期には神経系の正常な発達に関わるタンパク質で、障害を受けた神経の修復にも関わっていると言われています。疼痛の伝達にも関わっていると言われていて、NGFに対する抗体を体内に入れることでNGFの作用を阻害して痛みを緩和する目的で抗NGF抗体が使われます。
過去のブログ(←過去のブログにとびます)でも抗NGF抗体治療薬について触れています。
日本国内にはリブレラ(犬用抗NGF抗体薬)とソレンシア(猫用抗NGF抗体薬)が流通しています。
本セミナーはUSにおけるリブレラとソレンシア臨床使用の最近の話題(榎本先生)、犬OAの内科治療に入る前に必ずチェックすべき外科的ポイント(林先生)、猫OAの内科治療に入る前に必ずチェックすべき外科的ポイント(枝村先生)の3本で構成されていました。
ちなみにOA=Osteo arthritisとは関節軟骨の変性と破壊、関節辺縁や軟骨下骨における骨増生、二次性滑膜炎を伴う、進行性かつ非感染性の関節疾患です。
まず1本目の榎本先生ですが、NGFの持っている性質や抗NGF抗体薬の動物における効果や副作用、使用に関するガイドラインなどについてお話されていました。
中でもリブレラ投与後に神経症状が発生するリスクありとのお話は初めて聞いたこともあって興味深く聞かせて頂きました。
ただしリブレラ投与後に神経症状を表した症例のうちほぼすべての症例で脳腫瘍・椎間板ヘルニア・髄膜炎などの基礎疾患が見つかったらしいので本当にリブレラの副作用なのかも疑わしい気がしました。
榎本先生はリブレラ投与前に整形外科的な検査や神経学的検査を行うようにして、触診で関節の腫脹や肥厚が見つかった際にはレントゲン検査を実施してくださいとお話されていました。
2本目の林先生は跛行や歩きたがらないなどのOA徴候を示している犬における鑑別疾患として、整形外科手術が必要な疾患(膝蓋骨内方脱臼・前十字靭帯断裂・骨折など)、腫瘍、自己免疫性あるいは感染性関節炎、OAと併発していることが多い椎間板ヘルニア・馬尾症候群・脊柱管狭窄症などを挙げて、本当にその症状はOAによるものなのかをきちんと調べてから治療すべきだとお話されていました。また関節疾患に対する安易な内科(薬物)治療は危険だとも話されていました。
3本目の枝村先生は猫のOAについてお話されました。
枝村先生は、12歳以上の猫100頭に対する調査で90%の猫にOAが存在したという報告や6歳以上の家庭猫100頭に対する調査で61%の猫に少なくとも1か所以上の関節にOAがあり、14歳以上の猫の82%に少なくとも1か所以上の関節にOAがあったという報告を紹介していました。
同時に保険会社の調査によると動物病院で治療を受けた猫のなかで運動器疾患で診察を受けた猫は2%という疫学も紹介していました。
高齢の猫の多く(82-90%)にOAがあるにも関わらず運動器疾患で診療を受けている猫が2%しかいないということは、つまり猫の運動器疾患は気付かれにくいということですね。
当院でも爪が伸びて来てパッドに刺さりそうあるいは刺さってしまったというような高齢猫さんがたまに来院されますが、ほとんどの場合痛みによって爪とぎが十分にできていないことが原因だと思っています。
飼い主様に伺っても特に痛がっていないとお答えになることがほとんどです(爪が刺さって痛いという痛み以外の関節痛としては)。
猫は爪とぎはするけれど痛いからわざと爪が引っ掛からないようにしていても、比較的跛行もなく歩いてしまうので飼い主様が痛みに気付いてらっしゃらないのだと思います。
気が付かないから動物病院に行かないの結果が2%ということですね。
抗NGF抗体薬はOAによる痛みを感じている動物に対する治療の選択肢として大きな役割を担っていることは確かだと思いますが、注意して使うべき薬でもあると思います。
これからもきちんとした診断をしてから使うように飼い主様と協議していきたいと思います。